日本人が英語を難しいと感じてしまう、語順のお話
町で見かける外国人と気軽に会話ができたら、かっこいいのに。
英語が流暢に話せれば、もっと気軽に海外旅行に行けるのに。
我々日本人の中には、潜在的に英語が話せることへの憧れが、遺伝子レベルでうごめいていませんか?
以前に英語と日本語では、周りを見る順番が異なり、その認識の順に言葉を並べていくのだといったお話をしましたが、今回はその続きです。
日本語と英語における語順の役割とは?

たとえば、
The cat chased the mouse.
「その猫は、ねずみを追いかけた。」
という文章があったとき、
英語の語順を変えたらどうなるか?
The mouse chased the cat .
と主語と目的語の位置を入れかえると、
右の図のように、
「そのねずみは、猫を追いかけた。」
と文の意味は真逆になってしまいます。

一方、日本語の「その猫は、ねずみを追いかけた。」という文の語順を入れかえると、
意味はどう変わるのでしょうか。
- 1. 基本の語順
- その猫が、ねずみを追いかけた。
- 2. 目的語を先に置く
- ねずみを、その猫が追いかけた。
- 3. 目的語を最後に置く
- その猫が追いかけた、ねずみを。
- 4. 主語を最後に置く
- ねずみを追いかけた、その猫が。
日本語は語順が柔軟で、「が」や「を」といった助詞が意味を明確にするため、主語、目的語、動詞の順番を変えても文の意味は保持されます。
逆に、語順は同じでも、助詞を入れかえると、意味が変化します。
「その猫が、ねずみを追いかけた。」
「その猫を、ねずみが追いかけた。」
このように、日本語に親しむ我々は、文章の意味は語順ではなく、助詞でコントロールしていきます。
また、日本語は、「追いかける」「追いかけない」「追いかければ」といったように、語幹の「追いかけ」の後ろに色々な言葉がつくことで動詞の意味や役割を変えることができます。
しかし、英語の場合、語尾を変化させることで異なる時制を表したり、品詞を変える機能は持たせていますが、動詞の意味や役割を変える機能まではもたせていません。
chase (原形) 追跡する (名詞) 追跡
chases (三単現) 追跡する 主語による変化
chased (過去・過去分詞) 追跡した
chasing (動名詞)追跡すること (現在分詞)追跡している
英語には日本語の助詞にあたるものはありませんし、語尾を変化させても大きく意味を変化させてことはできません。
そこで、英語は語順を変化させることで相手に伝える意味も変化させることとしたのです。
したがって、英語は「位置言語」または「語順言語」と呼ばれるほど、語順が大切であり、語順によって意味が決まってくるのです。
語順を変化させて意味が変わる典型例は疑問文‼
英語を学び始めて最初に出て来る語順の変化は、疑問文の用法です。
たとえば、
She is happy. 彼女は幸せです。
という文章を疑問文にするとき、日本語では
彼女は幸せですか。
と語尾に「か」を付け加えれば、疑問の意味になります。
しかし、英語では、
Is she happy?
と主語とbe動詞の語順を入れかえることで、疑問の意味を表します。
通常の文(平叙文)では、主語の次にくるはずのbe動詞が文頭に置かれていることにより、聞き手、読み手はbe動詞を使った主語の存在や状態についての疑問について問われることを予測しながら、後の文に触れることが可能となります。
日本語では、語尾が「す。」なのか「か。」なのかを聞き逃すと、肯定なのか疑問なのかがわからなくなってしまうことに比べると、英語の方が、受け手の予測可能性が高まるように設計されているように感じます。
助動詞を含む疑問文は助動詞を前に出す。
be動詞以外の疑問文では、助動詞を主語の前に出します。
これにより、本来は、主語と動詞の間が定位置のはずの助動詞が前に出てきているという位置によって、質問をしたいという意志が明確になります。
普通の文: She can swim. 彼女は泳ぐことができます。
疑問文: Can she swim? 彼女は泳ぐことができますか。
このように、助動詞を前に出して、位置を変化させることで、聞き手は質問をされていることを即座に認識でき、コミュニケーションがスムーズに進み、誤解が減る。これは日本語にはないメリットと言えます。
中学校1年生で英語を本格的に習い始めた時に、どうしても、疑問文の語順の変化を忘れてしまう子がいるのですが、英語はどんな単語が並んでいるかだけでなく、その単語の位置と語順によっても意味がかわることを伝えると、語順を意識するようになりますので、間違いが減ってきます。
英語は位置や語順によって意味を伝えているということをもっと意識しても良いかもしれません。
一般動詞の疑問文では、Do、Dose、Didという助動詞が前に出て来る理由は?
英語初心者の答案を見ていると、be動詞を使った文の疑問文では、be動詞を前に出すのだから、一般動詞を使った疑問文も次のように、一般動詞を前に出してしまうという間違いをよく見かけます。
普通の文:He eats the cake.
間違った文:Eats he the cake?
たしかに、be動詞と同様のルールだと考えれば、一般動詞を前に出すというルールになるような気がします。
しかし、ここで重要なことは、英語は疑問文(ここでは詳しく触れるませんが否定文も)を作る時には、助動詞を文頭に出すという明確なルールを定めたということです。
それでは、be動詞は助動詞なの?という疑問を持ったあなた。するどい!!
be動詞は助動詞としての役割を持っています。
たとえば、現在進行形。be動詞+ing形で表されると説明されますが、厳密に言うと
「助動詞」としてのbe動詞+「現在分詞」としての動詞ing
という形で成り立っているように、be動詞には助動詞の役割があります。
疑問文の際に文頭に出しているのも、動詞の役割だけでなく、助動詞の役割をも果たすからに他なりません。
すると、一般動詞にも助動詞としての役割があれば、そのまま文頭に出せば疑問文が成り立つことになりますが、多くの一般動詞に助動詞の役割はありません。 CF.助動詞としてのhave

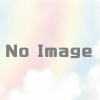

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません