英語に絶対不可欠なものは何?日本語で勘違いが発生する原因とは?
英語と日本語の考え方の違いとは?
あなたにこの本を貸してもいいよ。
I can lend you this book.
となります。ちなみに、
I=私は can=できる lend=貸す You=あたなに this book=この本という意味です。

このふたつの文を比べるとどんな違いがあるでしょう。
日本語の例文を見ると、英文の「I」に対応する「私は」が抜けています。
日本語では、話し手である「私は」をわざわざ言語化しません。
その場にいるのだから言わなくても伝わるでしょ?ということでしょう。
ここでの、日本語での例文である、「あなたにこの本を貸してもいいよ。」という文を省略のない日本語に置き換えると、
「私は、あなたにこの本を貸すことができます。」となります。
このように、主語を省略せずに表記すれば、誤解や勘違いは生じにくくなります。
しかし、日常の会話では、場に入り込んだ人どうしは、誰のことを言っているか伝わるはずという感覚が強いため、日本語では話の主人公であるはずの主語が省略されてしまい、結果として、
いったい誰のことについて話しているのかわからず、会話において誤解や勘違いをすることが
少なくありません。
一方、英語の場合、話し手が場に入り込んでいて、わざわざ「私が」と主語を示さなくても誰のことがわかるような状況であっても、言語の明確さと文脈の適切な伝達のために、登場人物を示すことがルールになっているため、必ず「主語」を示します。
言い換えれば、すべての場面を客観的に一枚の絵のようにとらえて、その状況を述べていくのが英語の特徴といえよう。
命令文など、一部主語を省略するような場合はありますが、「主語」を絶対不可欠のものとする点で日本語と英語には違いがあるといえます。
英語の主語になるものには、何がある?
英語では原則として主語が必要になるため、どんなものが主語になるのかを、知っておく必要がある。
結論から言うと、主語になりうるものは、「名詞」である。
名詞には大きく分けて、4つある。
まずは、「固有名詞」。人名やひとつしかないもの。聖徳太子や富士山などが固有名詞にあたり、主語になりうる。
次に、「普通名詞」。一般的なものの名前で、聖徳太子や富士山を普通名詞であらわすと、男性、山、となる。
そして、数や量など数字が関係するものは「数詞」。一番・二か月・三つ・四メートル・五人などがそれである。
最後に、最もよく使われるものとして、人や物事を指し示すものは「代名詞」がある。
英語は、日本語と違いアルファベット26文字の組み合わせだけでしか表現できないため、漢字や平仮名が使える日本語に比べて、つづりが長くなる。
たとえば、富士山も英語では正式に書くと Fuji Mountain となり、非常に長い。したがって、文の中で2回目以降は、It「それ」として表したい。
Itの他に、You、He、Sheなども代名詞として主語になる。
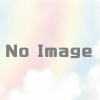

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません